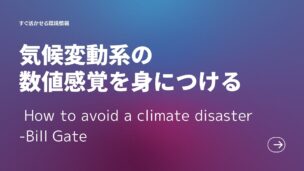サステナビリティに関心が高まる中、森林保護が気候変動対策として重要視されています。特に、成熟した老齢林が果たす役割について最新の海外研究をもとに詳しく解説します。
この記事のポイント
- 古い森林は若い森林よりもはるかに多くの炭素を保持している。
- 老齢の木も依然として十分なCO₂を吸収することが明らかに。
- 既存森林の保護は新たな植林より短期的な気候対策効果が高い。
古い森林は巨大な炭素の貯蔵庫
2023年に発表されたアメリカの研究によれば、成熟した森林は新たに植林された若い森林と比較して、約2倍以上の炭素を蓄積しています。例えば、アメリカ北東部の約160年の老齢林は、約80年の若い林に比べて地上部の炭素量が2倍以上多いことが確認されています。
老齢林でも十分なCO₂吸収能力
「古い木は成長が鈍るため、CO₂を吸収しない」という考えは誤解であることが最近の研究で明らかになりました。イギリスのバーミンガム大学の研究(2022年)によると、180年生の成熟したオーク林は高いCO₂濃度の環境下でも年間9.8%の成長量増加を示し、老齢の木も活発にCO₂を吸収していることが確認されています。
また、樹齢約100年の木は30年ほどの若い木より年間のCO₂吸収量が平均2.5倍も多く、古い木ほど葉の総量が多いため、全体的により多くのCO₂を吸収しています。
森林伐採による深刻な炭素放出
森林伐採により、長期間蓄えられた炭素が急激に放出されます。世界全体で森林は年間約160億トンのCO₂を吸収していますが、伐採や火災などで81億トンが再放出され、森林のCO₂吸収効果が大幅に相殺されているのが現状です。
米国オレゴン州では、過去に蓄積された炭素の65%が森林伐採を通じて再び大気中に放出されたという報告もあり、既存の森林を守ることが極めて重要です。
植林よりも森林保護を優先すべき理由
新たな植林は長期的に意味がありますが、気候変動の緊急性を考えると、既存森林の保護がより重要です。2023年の研究では、森林の減少を防ぐことで得られる炭素保全効果は、同じ面積に新たに植林をする場合の約2倍になることが示されています。
また、地球規模での分析では、森林を適切に保護することで約2,260億トンの炭素吸収が可能であることが示されていますが、その61%は既存森林の保護と成熟化で達成できます。
まとめと提言
古い森林を守ることは、地球温暖化を防止する最も迅速かつ効果的な方法です。私たち一人ひとりが森林保護の重要性を理解し、森林を守るための活動や政策を支援することが求められています。
参考文献
- 米国森林研究 (2023年)
- バーミンガム大学 FACE実験 (2022年)
- Global Forest Watch レポート (2023年)
本記事は、最新の海外研究を基にChatGPTのDeep Research機能を活用して作成しました。